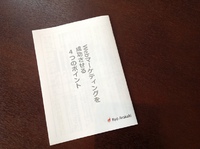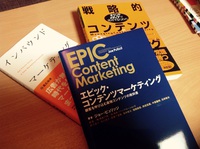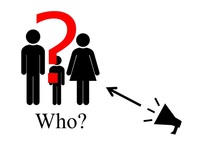2014年01月08日18:41
■今年の新成人の使用している「デジタル機器」は?
詳細はこちら
スマートフォンが増えている。
Androidが多いのは想像がつきますね。
この活用している「デジタル機器」の項目に「ウェアラブル」が今年中に入ってくるのでしょうか?
若者たちに選ばれるのかどうか?
要チェックです。
■SNS利用率は91.2%
今年の新成人のSNS利用率は
LINEが81.6%
Twitterが67.0%
Facebookが48.8%
mixiが18.0%
Google+が11.2%
※株式会社マクロミル調べ
詳しくは→こちら
やはりLINEが強いよねー。
意外とmixiとGoogle+もいるんだねー。
が僕の感想。
情報収集にはFacebookの方が向いていると思うんだが、それは僕がおっさんだからだろうか?
なんせ、若者はLINEなのである。
(LINE依存しないことを祈る)

↑
僕らの時代、かろうじてiモードのメールが流行りだしたころで、ほとんどのコミュニケーションは「直接会って話す」ことであった。
それにより、相手の感情がより伝わり、一緒に笑い、時に喧嘩もしたものだ。
テクノロジーの発展により、「直接会わなくても気軽にコミュニケーションができる時代」にはなったが、深いことが話せるのだろうか?
僕にはちょっと疑問。
スタンプのみのコミュニケーションって・・・いったい・・・
メールやメッセージだからこそ深い相談ができるという考えももちろんあるだろうが・・・
やはり、「直接会う」という「リアル」をもう少し増やせる工夫が必要なのでは?とひとり頭を悩ますのである・・・が、
たぶんそれは大きなお世話でもある。
何が言いたいかって?
テクノロジーの発展はすんごい。
これが言いたかったのだ。
以上。
また明日。
【SNS利用率91.2%】今年の新成人はほとんどがSNS利用。中でもLINEは強し。
■「Changing the way we live」
まずは「米インテル」のお話。
語りかけたのは「米インテル」のブライアン・クルザニッチ最高経営責任者(CEO)。
国際家電見本市「コンシューマー・エレクトロニクス・ショー(CES)」の開会を宣言でのひとコマのようです。
※詳細は日本経済新聞より→こちら
インテル=パソコン
というイメージだが、彼が終始語ったのは「ウェアラブル端末」について。
ウェアラブル端末とは?
簡単に言うと
身に着けられる小さいコンピューター等。
スマホやタブレットが、「持ち運んで必要なときに取り出して使う」ものであるのに対し、「常時電源ONの状態で身に着ける事」を前提として開発されている端末のことを「ウェアラブル」という。
ウェアラブル画像色々→こちら
スマートフォンからタブレット
そして「ウェアラブル」へという時代の流れを象徴しているかのよう。
象徴というよりも、先取りと表現しようか。
僕ら一般生活者には、まだまだ「ウェアラブル端末」は身近ではないような気がします。
少なくとも、僕の周りには「ウェアラブル」を活用している方は見当たらない。
まぁー、活用してる人はいる思うんですが、
実際 僕はまだ未使用。
ウェアラブルに関して、「ウェアラブルは買いなのか?」で、記事にしたのですが、まだ未購入。
どちらにしろ、「ウェアラブル」はこれからのキーワードであることは、米インテルのブライアン・クルザニッチ最高経営責任者(CEO)の公演記事を読んでもよく解る。
■最近の若者は・・・
流行に敏感な若者たち。
じゃー、最近の若者は「ウェアラブル」を活用しているのかどうか?
それもまだのようです。
それでは若者はどんな「デジタル機器」を活用しているのか?
「今年の新成人」はどのようにテクノロジーとお付き合いしているのであろうか?
まずは「米インテル」のお話。
「Changing the way we live(我々の生き方を変えよう)」――。観衆に語りかけた言葉は実は自分たちに向けた言葉だったのかもしれない。
語りかけたのは「米インテル」のブライアン・クルザニッチ最高経営責任者(CEO)。
国際家電見本市「コンシューマー・エレクトロニクス・ショー(CES)」の開会を宣言でのひとコマのようです。
※詳細は日本経済新聞より→こちら
インテル=パソコン
というイメージだが、彼が終始語ったのは「ウェアラブル端末」について。
ウェアラブル端末とは?
簡単に言うと
身に着けられる小さいコンピューター等。
スマホやタブレットが、「持ち運んで必要なときに取り出して使う」ものであるのに対し、「常時電源ONの状態で身に着ける事」を前提として開発されている端末のことを「ウェアラブル」という。
ウェアラブル画像色々→こちら
スマートフォンからタブレット
そして「ウェアラブル」へという時代の流れを象徴しているかのよう。
象徴というよりも、先取りと表現しようか。
僕ら一般生活者には、まだまだ「ウェアラブル端末」は身近ではないような気がします。
少なくとも、僕の周りには「ウェアラブル」を活用している方は見当たらない。
まぁー、活用してる人はいる思うんですが、
実際 僕はまだ未使用。
ウェアラブルに関して、「ウェアラブルは買いなのか?」で、記事にしたのですが、まだ未購入。
どちらにしろ、「ウェアラブル」はこれからのキーワードであることは、米インテルのブライアン・クルザニッチ最高経営責任者(CEO)の公演記事を読んでもよく解る。
■最近の若者は・・・
流行に敏感な若者たち。
じゃー、最近の若者は「ウェアラブル」を活用しているのかどうか?
それもまだのようです。
それでは若者はどんな「デジタル機器」を活用しているのか?
「今年の新成人」はどのようにテクノロジーとお付き合いしているのであろうか?
■今年の新成人の使用している「デジタル機器」は?
所有し、利用しているデジタル機器は、ノートPCが77.0%、Androidスマートフォンが45.6%、iPhoneが33.8%、デスクトップPCが24.4%、携帯電話・PHS(スマートフォンを除く)が23.0%、タブレット端末(iPad、GALAXY Tabなど)が10.8%。前年調査と比べると、Androidスマートフォンが8.0ポイント、iPhoneが8.8ポイント上昇した一方で、携帯電話・PHSが19.0ポイント低下した。
詳細はこちら
スマートフォンが増えている。
Androidが多いのは想像がつきますね。
この活用している「デジタル機器」の項目に「ウェアラブル」が今年中に入ってくるのでしょうか?
若者たちに選ばれるのかどうか?
要チェックです。
■SNS利用率は91.2%
今年の新成人のSNS利用率は
LINEが81.6%
Twitterが67.0%
Facebookが48.8%
mixiが18.0%
Google+が11.2%
※株式会社マクロミル調べ
詳しくは→こちら
やはりLINEが強いよねー。
意外とmixiとGoogle+もいるんだねー。
が僕の感想。
情報収集にはFacebookの方が向いていると思うんだが、それは僕がおっさんだからだろうか?
なんせ、若者はLINEなのである。
(LINE依存しないことを祈る)

友達とのコミュニケーションについては、「直接会うことが多い」とした人が38.4%ある一方で、「友達のTwitterのつぶやきやFacebookの書き込みを見ることが多い」の28.5%、「メールで文章を送ることが多い」の19.2%、「Twitterでつぶやく、Facebookに書き込むなど不特定多数に向けての発信が多い」の18.8%、「写真やスタンプなどを使った文章の少ないショートメッセージを送ることが多い」の18.6%など、SNSやネットを使ったコミュニケーションも多かった(いずれも、各項目について「とでもあてはまる」と回答した人の割合)。
↑
僕らの時代、かろうじてiモードのメールが流行りだしたころで、ほとんどのコミュニケーションは「直接会って話す」ことであった。
それにより、相手の感情がより伝わり、一緒に笑い、時に喧嘩もしたものだ。
テクノロジーの発展により、「直接会わなくても気軽にコミュニケーションができる時代」にはなったが、深いことが話せるのだろうか?
僕にはちょっと疑問。
スタンプのみのコミュニケーションって・・・いったい・・・
メールやメッセージだからこそ深い相談ができるという考えももちろんあるだろうが・・・
やはり、「直接会う」という「リアル」をもう少し増やせる工夫が必要なのでは?とひとり頭を悩ますのである・・・が、
たぶんそれは大きなお世話でもある。
何が言いたいかって?
テクノロジーの発展はすんごい。
これが言いたかったのだ。
以上。
また明日。
コト商品開発に何が重要か?それは「○○でイケてるかどうか」
コト商品の情報発信には「○○」が大切
宣伝会議、広報会議のデジタル版定期購読を雑誌版に切り替えた私の理由。
インバウンド(外国人)ターゲット戦略のほうが効果がスピィーディー。
テレビもネットでライブ配信の時代。テレビ東京様ありがとうございます!
自社サイト、自社ブログの重要性に気づき始めたあなたへ。
Webマーケティングを成功させるコツ。
【Web担当の皆様へ】アクセス推移は平均値で見るとわかりやすい。
お客様から信頼されるということ。
沖縄イーコマース協議会の講座にお邪魔してきました。
コト商品の情報発信には「○○」が大切
宣伝会議、広報会議のデジタル版定期購読を雑誌版に切り替えた私の理由。
インバウンド(外国人)ターゲット戦略のほうが効果がスピィーディー。
テレビもネットでライブ配信の時代。テレビ東京様ありがとうございます!
自社サイト、自社ブログの重要性に気づき始めたあなたへ。
Webマーケティングを成功させるコツ。
【Web担当の皆様へ】アクセス推移は平均値で見るとわかりやすい。
お客様から信頼されるということ。
沖縄イーコマース協議会の講座にお邪魔してきました。